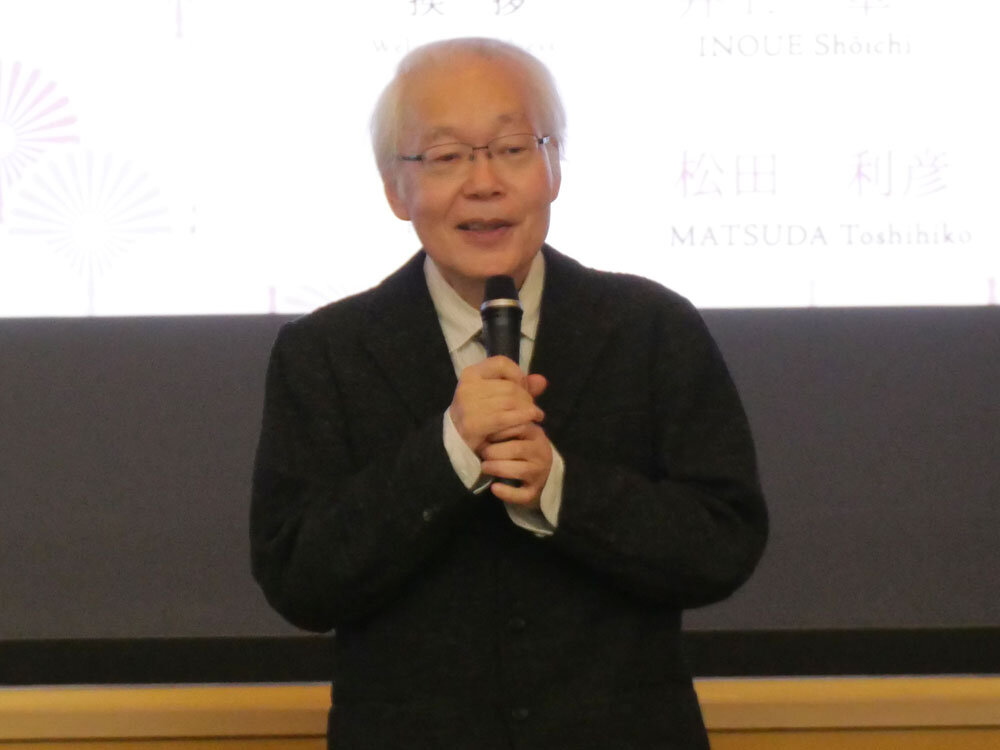[木曜セミナー・リポート]第282回日文研木曜セミナー「瀧井一博先生紫綬褒章受章記念講演会 知識としての日本―国際日本学が目指すもの―」(2025年2月20日)
2025年2月20日(木)、第282回木曜セミナーの場において、「知識としての日本―国際日本学が目指すもの―」と題する瀧井一博教授(日文研)の紫綬褒章受章記念講演会が松田利彦副所長(日文研)の司会の下に開催されました。
冒頭では井上章一所長(日文研)が瀧井教授の受章の祝辞を述べました。続く本講演で瀧井教授は、「知識としての日本」をテーマに、国際日本学の意義、知識国家の形成、日本における知識の交換と創発について論じました。
瀧井教授は、従来特殊に描く傾向にあった日本学という学問の在り方は現在再考を迫られている。そのためには、日本に関わる学問をつなぎ、統合し、体系化する学問として、国際日本学というジャンルを打ち立てる必要があるのではないか、という問いを立てました。
この発想に思い至った経緯として瀧井教授は、かつて参加した日文研での戸部良一教授(現名誉教授)の共同研究会で聴講した、埼玉県川越市でクラフトビールを起業した株式会社協同商事コエドブルワリーの朝霧重治代表取締役社長のお話から、「知識を世界に届けるメディアとしての日本」という考え方を示唆されたという興味深いエピソードを披露しました。
さらに、著名な日本研究者であるアンドルー・ゴードン教授とのサントリー文化財団グループ研究プロジェクトにおいて、「問題先進国」としての日本というアイデアに触れたことについて言及しました。日本は少子高齢化や気候変動による環境変化、自然災害と復興という課題に直面していますが、それらは日本だけの問題ではなく、世界中の国が今後直面することが予想される問題でもあり、こうした世界共通の問題に先導的に取り組むことで、日本は世界に何らかの貢献ができる立場にあると述べました。また、その際には経営学の泰斗である野中郁次郎教授が述べた知識経営論を応用し、知識を創造し、循環させる存在として、知識創発の場として国家を考えていく必要があるのではないかと語りました。
そして瀧井教授が知識国家の具体的な事例として取り上げたのが明治維新でした。明治維新は尊王攘夷や富国強兵、公議公論がキーワードとしてよく取り上げられますが、ここにさらに「衆知」、「知識交換」を加えたいと述べました。なぜならば明治維新とは、江戸時代からの豊富な在野の知識を活用した知識革命でもあったからです。
この知識国家の確立に貢献した三人の人物として、瀧井教授は自身が研究対象として取り組んできた伊藤博文、渡邉洪基、大久保利通を取り上げました。
若くして日本のリーダーとなった伊藤は、憲法調査によって、ウィーンのローレンツ・フォン・シュタイン教授から国家学を学び、憲法とは単に導入すればよいものではなく、国制知がドイツを保ってきたということを伝授されました。そして、伊藤はこのシュタインの教えに加えて、憲法に先んじて帝国大学を創設して官僚養成の学府とすることで、憲政を補完する行政の整備に取り組み、また衆知を結集する場として立憲政友会を立ちあげました。
この伊藤の側近で初代帝国大学総長となった人物が渡邉洪基です。渡邉は伊藤の意を受けて、大学の創設及び様々な学会の創設に取り組みましたが、彼の原点には知の結社活動があり、日本各地のイノベーションの試みを中央に吸い上げて、知識を循環させ、政策提言を行うシンクタンクを先駆的に構想しました。
そして志半ばで凶刃に斃れたものの、伊藤の先達者として知識革命としての明治維新をリードしたのが大久保利通です。大久保は明治新政府を打ち立てたのち、新国家建設のために日本各地に潜在する知の担い手たちを見出し、そのような人たちを結びあわせることで殖産興業を成し遂げようとしました。明治期の日本とは、新国家建設のために西洋の知識を単に輸入するのではなく、在野の知を取り入れつつ、お互いに刺激し合う「知識交換」が活発になるようにリーダーたちが率先して取り組んだ時代であったと瀧井教授は主張しました。
このように、知識交換を誘発する場として日本を再生することが重要であると瀧井教授は強調しました。日本という時空間で生じた知識を結び合わせ、新たな知識を創造していくことが、今後の日本学が目指すべき方向ではないか。世界とつながっていくグローバルな知識交換のメディアとしての日本を打ち立てる必要があるのではないかと瀧井教授は主張し、これからは「日本とは何か」から「日本に何ができるか」へと考えていくことが大事であるとして、講演を締めくくりました。
瀧井教授のこれまでの壮大な研究が取りまとめられ、知的な啓発に富む紫綬褒章の受章記念講演でありました。その後の懇親会もまさに「知識交換」の場となりました。瀧井教授の今後のさらなるご活躍とご健康を祈念いたします。
(文・西田彰一 プロジェクト研究員)