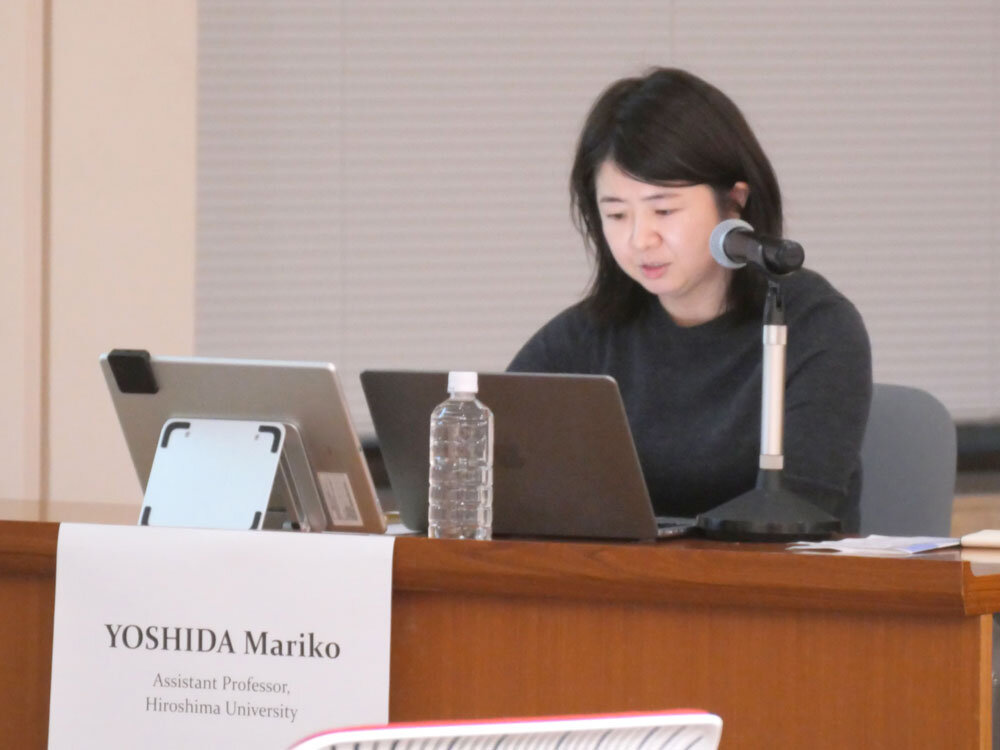[Evening Seminarリポート]「The Transpacific Tidelands of the Pacific Oyster」(2024年10月3日)
2024年10月3日、第258回日文研イブニングセミナーにおいて、シエル・エリクソン氏(京都大学特任講師)にご講演いただきました。コメンテーターとして吉田真理子氏(広島大学助教)をお招きし、司会はエドワード・ボイル(日文研准教授)が務めました。「The Transpacific Tidelands of the Pacific Oyster」と題した本発表では、付着生物・牡蠣の人工的移植、具体的には東北地方に生息する牡蠣がアメリカ大西洋のワシントン州沿岸へ運ばれたことについて議論されました。本発表は、エリクソン氏とマシュー・ブッカー氏(ノースカロライナ州立大学教授)が進める共同研究プロジェクトである日本とアメリカに関する資料調査がもとになっています。
発表では、日本とアメリカの牡蠣貿易の歴史という、太平洋を横断しつつも非常に地域的な話題に焦点があてられました。前半では、原産地・東北の松島湾からワシントン州への牡蠣の輸出、そしてワシントン州干潟での飼育について議論されました。この貿易は元々、宮城新昌によって推進されました。宮城は、日本人漁業事業家たち、特に牡蠣生産者たちの太平洋をまたいだ活動促進に貢献した人物です。近年、東栄一郎やその他の研究者により、日本の国境なき帝国という概念が議論されていますが、それが一つの形で顕現した事例といえるでしょう。1920年代、日本からアメリカへの人の移動や移住は激減しましたが、牡蠣貿易自体は太平洋戦争に至るまで拡大の一途をたどっていました。エリクソン氏は、越境帝国的な牡蠣貿易の歴史は、移植、定着性と移動性についての問題、そして水陸に対する近年の関心を示していると指摘しました。
日本・アメリカ間の競争は、牡蠣が「太平洋原産」の生物として再ブランド化されることで激化しました。これにより、牡蠣は外洋起源であるにもかかわらずアメリカ産とみなされるようになりました。そして、戦後の牡蠣貿易再開は戦後の日米関係に関する一連の議論のひとつとなりました。1940年代の牡蠣独立養殖の試みは、ワシントン州沿岸の環境条件が原因で頓挫しました。つまり、成長した牡蠣を飼育し収穫することはできても、牡蠣の繁殖や育成は他の場所で行う必要があったのです。戦後に牡蠣貿易が再開されると、東北の漁村は、アメリカのワシントン州の法律に従うことを強いられました。地元民は外国の法律が定める検査を受けることになり、国内外の貿易団体は日本の農林水産省の官僚と規制をめぐり攻防を繰り広げました。当時の日本の官僚たちは、牡蠣貿易にかかる規制が、日本の主権や、自国の正当性や国際的な権威を再構築しようとする戦後日本の自立性や尊厳に対して、潜在的な影響を与えるのではないか、とはっきりと自覚していました。エリクソン氏は、この規制をめぐる攻防は連合国軍占領下でのみ行われたのではないと指摘します。結局このような状態は、宮城での収穫量の減少や韓国や台湾から牡蠣が代替供給されたことにより、ワシントン州産の牡蠣のシェアが低くなる1970年代まで続きました。
このような短いレポートでは、本研究の豊かさを十分に伝えることは難しいと言わざるを得ません。本研究には、日本とアメリカの水産養殖の構想の違いや、それらがどのように各地域で法的に定められているのかという問題も含まれています。ワシントン州の干潟の権利制度は、オレゴン州やカリフォルニア州など他の西海岸の州とは異なります。ワシントン州における牡蠣養殖は、限られた環境条件と独特な法的枠組みの中で行われています。また、本研究は、環境と人の移動との関係、そして貿易によってみえてくる様々な時間的・地理的スケールを明らかにしています。
本研究の概念的な豊かさについては、コメンテーターの吉田氏からも言及がありました。また、吉田氏は、本研究が人種化や自然の国有化、異種間・同種内協働の異なる形態など 、本研究が扱う事項を指摘しました。さらに、本研究が食料供給に関わる問題についての考察を扱う点において、アナ・ツィンの太平洋を横断した松茸研究との類似性があると指摘しました。
その後の議論では、本研究に開かれた生産的な今後の展開について語られました。日文研は、太平洋の両側からなされる真に国際的なこの日本研究プロジェクトから、どのような成果が得られるのかを心待ちにしています。
(文責・エドワード・ボイル准教授)