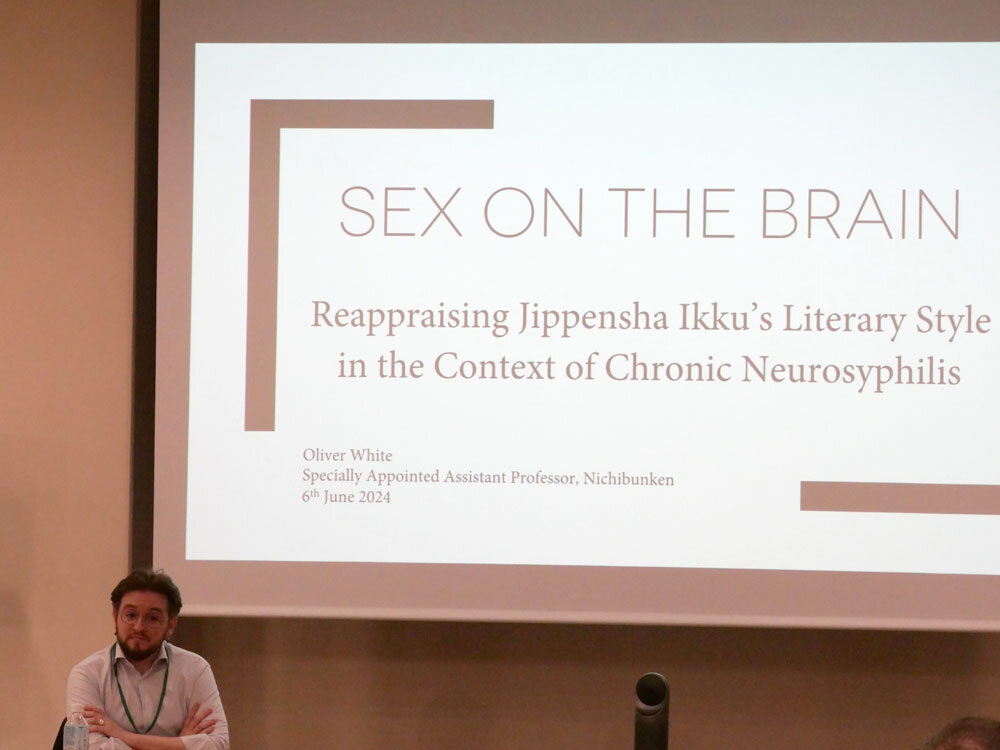[Evening Seminarリポート]「Sex on the Brain: Reappraising Jippensha Ikku’s Literary Style in the Context of Chronic Neurosyphilis」(2024年6月6日)
2024年6月6日(木)、「Sex on the Brain: Reappraising Jippensha Ikku’s Literary Style in the Context of Chronic Neurosyphilis」と題し、第257回日文研イブニングセミナーが開催されました。発表者はオリバー・ホワイト特任助教(日文研)、コメンテーターはマシュー・ショアーズ氏(シドニー大学上級講師)、司会は坂知尋プロジェクト研究員(日文研)が務めました。
十返舎一九(1765-1831)は江戸期滑稽本『東海道中膝栗毛』およびその続編の作者として知られています。弥次郎兵衛と喜多八が江戸から京都・大阪へ旅し、伊勢に参詣する道中を描いたこれらの作品には、作者の豊富な旅行経験が反映されており、大変な人気を博しました。しかし、後期の作品については、独自性に欠ける・くどいなどといった評価があり、その質が疑問視されているといいます。今回の発表では、一九の健康状態、具体的には慢性神経梅毒疾患が創作活動に影響していたのではないかという視点から考察がなされました。
ホワイト氏は、まず、一九が吉原通いを通じて梅毒の危険にさらされていた可能性を指摘しました。一九は、「入り浸っていた」と表現されるほど頻繁に吉原に出入りしており、作品からも彼が吉原の習慣や文化に精通していたことが伺われます。当時、江戸の人口の4~7割が梅毒に罹患していたともされ、吉原などの風俗街で働く女性たちの間でも蔓延していました。
また、晩年の一九の様子を伝える資料は、彼が何らかの慢性神経疾患に罹患していたことを示しているといいます。なかでも、脳卒中や身体麻痺、精神不安に関する記述は、慢性神経梅毒の症状と一致しており、後期作品の質の低下や文筆活動の消極化は梅毒からくる心身の不調に起因するのではないかとの見解が示されました。驚いたことに、没年の1831年に発刊された『続々膝栗毛』最後の2巻をはじめ、1823年以降に発表された多くの作品の実際の作者は別人である可能性が高いといいます。
さらに、一九が目の不調を訴え梅毒治療にも用いられる湯治を何度も行っていたことや、神経梅毒の症状に目の病変が含まれること、梅毒に関する描写や冗談が作品中にいくつも盛り込まれていること、そして、1805年以降の一九の行動や出来事(多作、息子の死、取材旅行の中止、消極化した作画活動など)に神経梅毒の影響がみられると指摘されました。また、浮世絵師・墨川亭雪麿(1797-1856)が一九を酔いどれと批判し対立した事件は、実際には神経梅毒による言語障害や精神不安に起因していた可能性があることも述べられました。
コメンテーターのショアーズ氏は、神経梅毒と一九の関係はこれまでの研究では注目されてこなかったことだとし、作者とその作品に対する新しい見方が示されたと評しました。また、江戸から地方への旅を描写した『膝栗毛』シリーズは、読者に旅の体験と醍醐味、注意事項を伝えるとともに、江戸中心の文学からの転換をもたらした作品であると述べました。
質疑応答では、同一人物が執筆と作画の両方を手掛けるのはよくあることなのか、一九の作画活動は具体的にいつからどれくらい減ったのか、創作的要素が多分に含まれる文学作品中の描写はどの程度実際の様子や事柄を伝えているのか、一九の罹患はなぜ知られていなかったのか等の質問が相次ぎ、セミナー終了後も会場参加者間で活発な意見交換が行われました。
(文・坂知尋 プロジェクト研究員)