「大学共同利用機関シンポジウム2025」を開催しました(2025年10月4日)
2025年10月4日(土)、日文研の講堂において、「大学共同利用機関シンポジウム2025」を開催しました。今年は「大学共同利用機関って何?」をテーマに、日本全国の大学共同利用機関が一堂に会するこの機会に、世界的に見ても極めてユニークな機能を持つ、大学共同利用機関の役割や課題を共有することを目的に実施しました。
開会にあたり、井上章一所長(日文研)が挨拶を行い、続いて淵上孝氏(文部科学省研究振興局長)より祝辞が寄せられました。その後、3つのテーマを軸にしたセッションが行われ、研究者だけではなく、現場の技術職員等も含めた多様な立場から16名の登壇者が発表と討議を行いました。
セッション1は「大学共同利用機関の役割と機能-大学共同利用機関だからこそできること-」と題し、谷口真人氏(総合地球環境学研究所特任教授)の司会のもと、個々の大学では維持が困難な大型設備や資料等の共同利用の提供だけではなく、各機関と関連した研究者コミュニティや研究分野から求められる中核的な役割や連携のあり方等を議論しました。後田裕氏(素粒子原子核研究所教授)による国際共同研究「Belle II実験」の報告や、定藤規弘氏(生理学研究所特任教授)による分子科学と生命科学の融合構想、工樂樹洋氏(国立遺伝学研究所教授)によるDNA情報学を通じた生物多様性研究、高田智和氏(国立国語研究所共同利用推進センター長)による言語資料のオープン化など、多様な分野から共同研究や共同利用の実践例が示され、パネルディスカッションでは、大学共同利用機関が日本の学術基盤を支える中核的存在として、研究者コミュニティを「引き上げる」と同時に「押し上げる」機能を担う重要性が再確認されました。
セッション2は、「大学共同利用機関の共同利用を支える-技術系スタッフの役割-」と題し、関野樹教授(日文研)が司会を務め、研究を根底で支える技術職員や司書等の専門性に光が当てられました。村瀨尊則氏(核融合科学研究所技術部設計開発技術課技師)による大型装置運用の現場報告や、牧村俊助氏(素粒子原子核研究所 先任技師)による加速器技術の開発事例、中藤亜衣子氏(国立極地研究所南極隕石ラボラトリー学術支援技術専門員)による南極隕石のキュレーション、酒井康平氏(国立歴史民俗博物館管理部博物館事業課主任/技術職員)による資料撮影技術の紹介など、各機関での実践が共有されました。また、江上敏哲資料利用係長(日文研情報管理課)が図書館を知の共有基盤と位置づけ、デジタルアーカイブ化と標準化の重要性を論じました。パネルディスカッションでは、技術系人材の育成や技能継承の重要性が強調され、技術者が知の創造に不可欠であることが再認識された一方で、予算の減少等に伴う後進の育成の難しさなどにも話が及びました。
セッション3は、「社会とともに歩む大学共同利用機関-よりよい未来を築くための連携の形を探る-」と題し、駒居幸特任助教(日文研)が司会を務め、各機構や機関がそれぞれの特色を生かして実践している「よりよい未来」に貢献するための社会連携の事例を共有し、大学共同利用機関が社会に求められる姿やあるべき協働の形について考察しました。足立伸一氏(高エネルギー加速器研究機構理事)はKEKが実施する文理融合や国際的ネットワークによる従来の研究者コミュニティを超えた新しい連携の取り組みを紹介し、中村敏和氏(分子科学研究所特任部長(研究戦略担当)/チームリーダー)は大学共同利用機関ならではの社会連携という視点から自然科学研究の横断的推進の意義と利点を述べました。さらに、岡本基氏(統計数理研究所 運営企画本部企画室URAステーション主任URA/特任准教授)は公的統計ミクロデータの利活用を促進するオンサイト施設の事例を紹介し、松尾瑞穂氏(国立民族学博物館教授)は大学共同利用機関としての博物館の機能という観点から社会連携を捉えなおしました。パネルディスカッションでは、データ標準化や異分野連携の課題、学術資源の社会還元などが活発に議論され、大学共同利用機関が「学術と社会の共創」を担う場としての更なる可能性が示されました。
終盤では、各セッションの司会者による総括が行われ、大学共同利用機関は研究者のネットワーク形成を促し、多様な出会いと対話を通じて知のあり方そのものを更新する「場」であることが改めて確認されました。閉会にあたり、大学共同利用機関協議会長を務める土居守氏(国立天文台台長・大学共同利用機関協議会会長)は、次世代の研究者・技術者を育成しながら、開かれた学術基盤を未来へ継承する意義を強調しました。本シンポジウムを通じ、大学共同利用機関は単なる研究リソースの共有を提供する拠点ではなく、知の生産・循環・社会還元を担う学術の中核的ハブであることが再認識されました。今回の試みでは、研究・技術・社会の三位一体による協働の重要性を大学共同利用機関が自ら広く発信する機会となり、今後の日本の学術の発展に向けた新たな出発点として意義深い一日となりました。
本シンポジウムは、大学共同利用機関協議会及び一般社団法人大学共同利用研究教育アライアンスによる主催、文部科学省の後援により実施されました。当日はYouTubeでもライブ配信され、現地及びオンラインにて171名の参加がありました。その模様は、今後も引き続きアーカイブ配信でお楽しみいただけます。
日文研公式YouTubeチャンネル「大学共同利用機関シンポジウム2025」
https://www.youtube.com/live/ZROG9WDpQZw
(報告:総合情報発信室)
-
 井上所長(日文研)による開会挨拶
井上所長(日文研)による開会挨拶
-
 淵上研究振興局長(文部科学省)による来賓挨拶
淵上研究振興局長(文部科学省)による来賓挨拶
-
 登壇者及び木部人間文化研究機構長
登壇者及び木部人間文化研究機構長
-
 大学共同利用機関関係者
大学共同利用機関関係者
-
 谷口特任教授(総合地球環境学研究所)
谷口特任教授(総合地球環境学研究所)
-
 後田教授(素粒子原子核研究所)
後田教授(素粒子原子核研究所)
-
 定藤特任教授(生理学研究所)
定藤特任教授(生理学研究所)
-
 工樂教授(国立遺伝学研究所)
工樂教授(国立遺伝学研究所)
-
 高田共同利用推進センター長(国立国語研究所)
高田共同利用推進センター長(国立国語研究所)
-
 関野教授(日文研)
関野教授(日文研)
-
 村瀨技師(核融合科学研究所)
村瀨技師(核融合科学研究所)
-
 牧村先任技師(素粒子原子核研究所)
牧村先任技師(素粒子原子核研究所)
-
 中藤学術支援技術専門員(国立極地研究所)
中藤学術支援技術専門員(国立極地研究所)
-
 酒井博物館事業課主任/技術職員(国立歴史民俗博物館)
酒井博物館事業課主任/技術職員(国立歴史民俗博物館)
-
 江上資料利用係長(日文研)
江上資料利用係長(日文研)
-
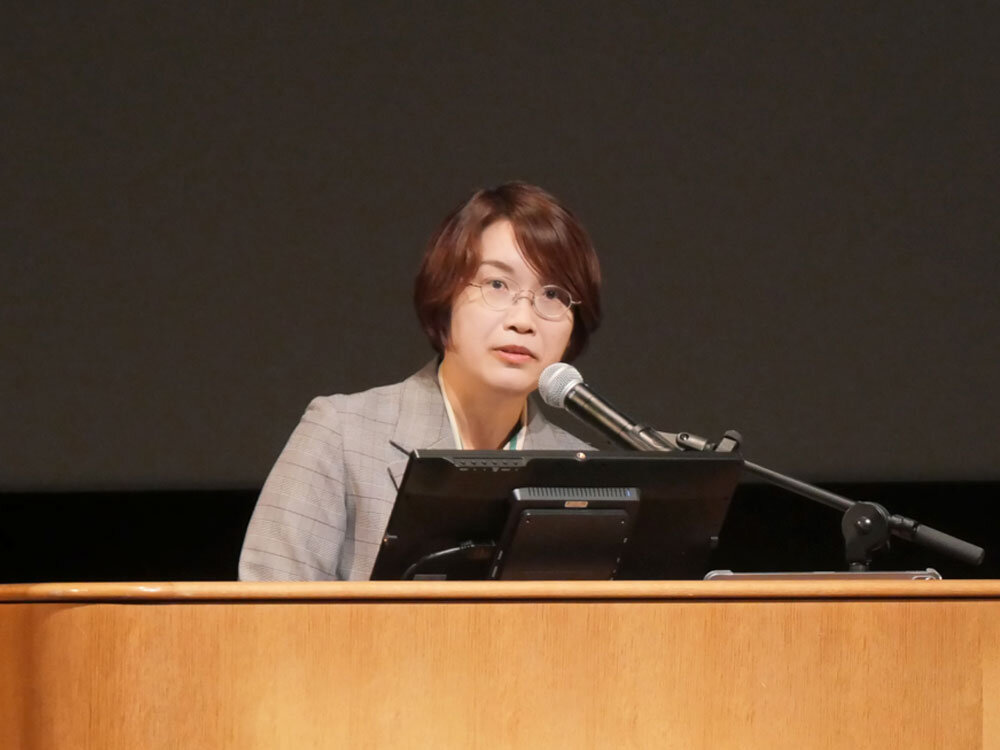 駒居特任助教(日文研)
駒居特任助教(日文研)
-
 足立理事(高エネルギー加速器研究機構)
足立理事(高エネルギー加速器研究機構)
-
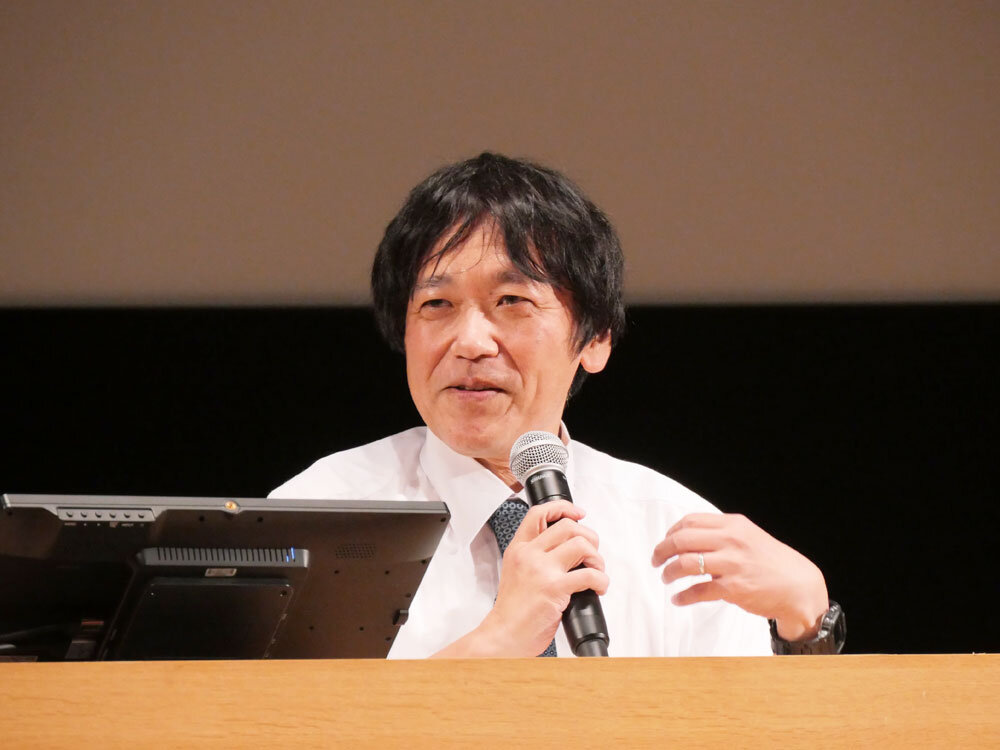 中村特任部長(研究戦略担当)/チームリーダー(分子科学研究所)
中村特任部長(研究戦略担当)/チームリーダー(分子科学研究所)
-
 岡本主任URA /特任准教授(統計数理研究所)
岡本主任URA /特任准教授(統計数理研究所)
-
 松尾教授(国立民族学博物館)
松尾教授(国立民族学博物館)
-
 土居台長(国立天文台)による閉会挨拶
土居台長(国立天文台)による閉会挨拶

